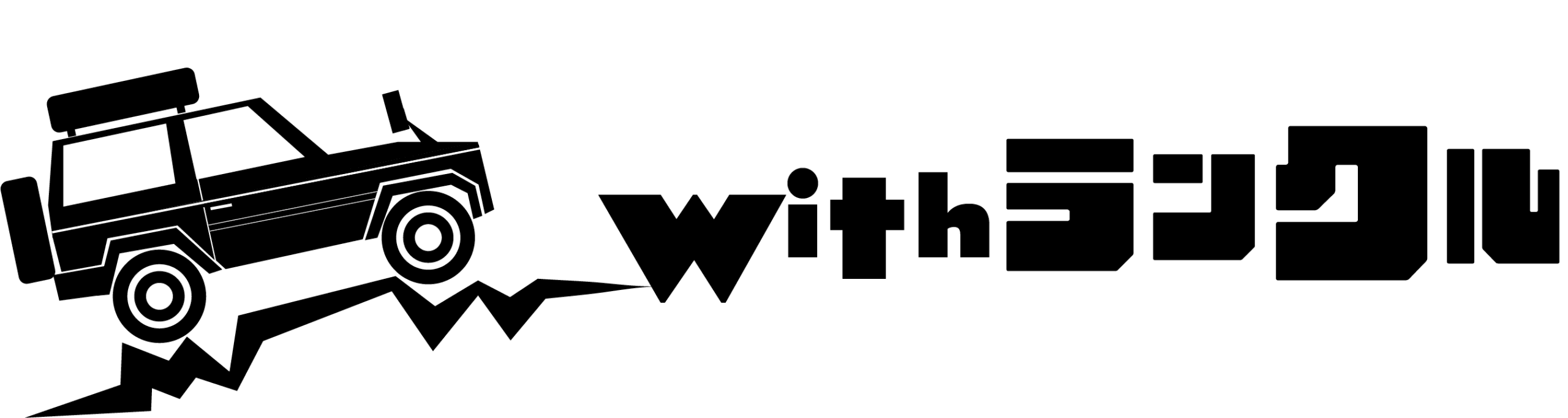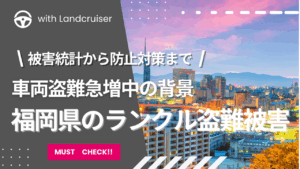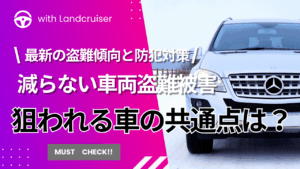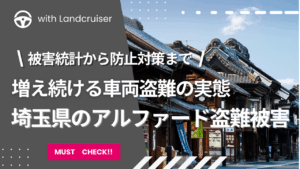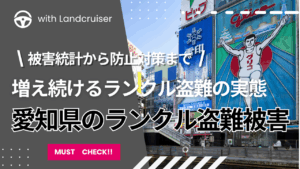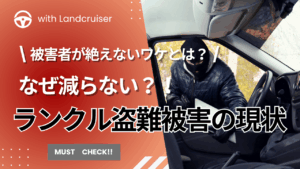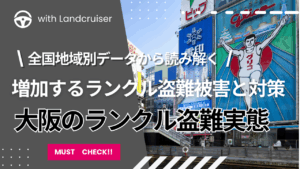近年、車両盗難の手口が多様化する中で、特に注目されているのが「CANインベーダー」と呼ばれる新たな手法です。
従来のリレーアタックやイモビカッターとは異なり、車の電子制御信号(CAN信号)に直接アクセスして、エンジン始動やドア解錠を行う極めて巧妙な方法です。
本記事では、CANインベーダーの基本概念や特徴、他の盗難手口との違い、対策方法、さらには盗難防止グッズの選び方や注意点までを、初心者にも分かりやすく解説します。

CANインベーダーとは?
CANインベーダーの基本概念
CANインベーダーは、車の通信ネットワークである「CAN(Controller Area Network)」に不正に接続して制御信号を操作する手口です。
車両のフロントライト周辺やバンパー裏にあるコネクタを経由して接続し、あたかも正規のキーがあるように見せかけてドアを開けたり、エンジンを始動させたりします。
CANインベーダーの特徴
この手口の最大の特徴は、物理的に鍵穴やドアを壊す必要がなく、車に痕跡を残さずに盗むことができる点です。
また、車のアラームやイモビライザーを無効化できることも多く、最新の高級車でも防げないケースがあります。
イモビカッターについての記事もぜひチェックしてみてください。
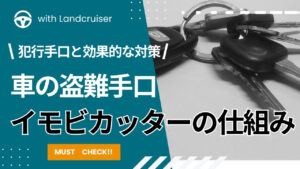
CANインベーダーと他の盗難手口の違い
リレーアタックやイモビカッターとの比較
リレーアタックはスマートキーの電波を中継して車両を解錠・始動する方法で、イモビカッターはイモビライザーを無効化する手口です。
一方、CANインベーダーは車の通信信号そのものにアクセスするため、スマートキーがなくても侵入・始動が可能です。

他の車両盗難手口との違い
CANインベーダーは車の電子制御の隙を突く最先端の手口であり、従来の物理的な破壊や鍵の複製といった方法とは根本的に異なります。
静音かつ短時間での犯行が可能なため、防犯対策がより難しくなっています。
狙われやすい車両の特徴
盗難のリスクが高い車両
高級SUVや人気のある国産車、特にトヨタ・レクサスなどの車種はCAN通信の仕様が広く知られており、狙われやすい傾向にあります。
海外でも需要が高く、輸出目的の盗難が多発しています。
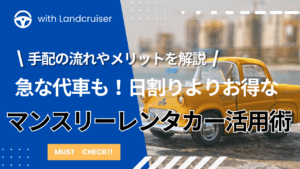
トヨタ車の盗難傾向
トヨタ車はCANインベーダーの主要な標的となっており、プリウス、アルファード、ランドクルーザーなどは特に盗難件数が多いとされています。
これらの車種は部品取りや海外転売の対象になりやすいのです。
CANインベーダーへの具体的な対策
物理的ロックタイプの対策
ハンドルロック、タイヤロック、ペダルロックなどの物理的な防犯対策は、CANインベーダーのような静かな盗難手口にも有効です。
時間を稼ぐことで、犯行を諦めさせることが期待できます。

電気的乗り逃げ防止タイプの対策
車内のOBD接続口を無効化する装置や、CAN通信を遮断するセキュリティデバイスを導入することで、通信経路へのアクセスを防ぎます。
最近では専用のCANガード装置も市販されています。
ダミースキャナーの活用
車内にLEDランプ付きのダミーセキュリティを設置することで、外部から見える抑止効果が期待できます。
安価で導入しやすく、他の対策と併用することで効果を発揮します。
盗難防止グッズの選び方
タイヤロックやハンドルロックの効果
物理的に車の操作を妨げるこれらのアイテムは、CANインベーダー対策としても有効です。
犯人にとって解錠の手間がかかるため、狙われにくくなります。

セキュリティシステムの導入
センサー付きの車両監視装置やGPS追跡システムを導入することで、盗難時の追跡や犯行の早期発見につながります。
スマートフォンと連動したシステムが人気です。

イモビライザーの活用
イモビライザー単体ではCANインベーダーには無力ですが、他の対策と併用することで防犯性が高まります。
複数の手段を組み合わせることが重要です。
CANインベーダー対策の限界と注意点
盗難対策の限界
いかなる対策も100%の防止は不可能であり、新たな手口が出現すれば突破される恐れがあります。
そのため、防犯意識を常に持ち続けることが重要です。
駐車環境のリスク
路上や照明の少ない場所に長時間駐車することはリスクを高めます。
自宅ではカーポートに監視カメラを設置するなど、駐車環境の改善も有効です。

盗難防止のための注意点
鍵の管理、セキュリティ装置の定期点検、駐車場所の工夫など、日頃からの小さな注意が盗難防止につながります。
複数の対策を同時に行うことで防犯力が格段に上がります。
車両盗難対策についてのより詳しい解説は、こちらのページでもご紹介しています。
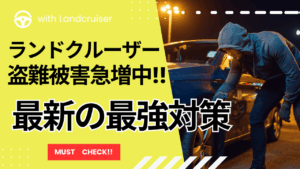
まとめ
CANインベーダー対策の重要性
CANインベーダーは最新の技術を用いた巧妙な盗難手口であり、従来の対策だけでは防ぎきれない可能性があります。
そのため、多層的かつ実践的な防犯対策が欠かせません。
今後の対策の展望
車両メーカーによるCANシステムの改良や、次世代型セキュリティデバイスの開発が進んでいます。
利用者側も最新情報を常にチェックし、対策のアップデートを行うことが大切です。